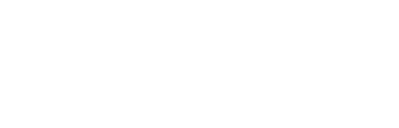市街化区域と市街化調整区域
松原市は全域が都市計画区域になっています。都市計画区域においては、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために都市の発展の動向などを考え、市街地として積極的に整備する区域である「市街化区域」と、市街化を抑制する区域である「市街化調整区域」を定めています。
- 市街化区域とは、すでに市街地を形成しているか、又は概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
- 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。
| 市街化区域 | 市街化調整区 | 告示 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 百分率 | 面積 | 百分率 | 年月日 | 番号 |
| 1135ヘクタール | 68.5% | 523ヘクタール | 31.5% | 昭和45年6月20日 | 府告第854号 |
| 1191ヘクタール | 71.8% | 467ヘクタール | 28.2% | 昭和53年12月27日 | 府告第1877号 |
| 1191ヘクタール | 71.8% | 467ヘクタール | 28.2% | 昭和61年6月16日 | 府告第859号 |
| 1206ヘクタール | 72.3% | 461ヘクタール | 27.7% | 平成6年4月27日 | 府告第798号 |
| 1253ヘクタール | 75.2% | 413ヘクタール | 24.8% | 平成13年3月16日 | 府告第407号 |
| 1279ヘクタール | 76.8% | 387ヘクタール | 23.2% | 平成18年3月17日 | 府告第637号 |
| 1282ヘクタール | 77.0% | 384ヘクタール | 23.0% | 平成23年3月29日 | 府告第418号 |
| 1313ヘクタール | 78.8% | 353ヘクタール | 21.2% | 平成27年3月30日 | 府告第520号 |
| 1324ヘクタール | 79.5% | 342ヘクタール | 20.5% | 平成30年3月28日 | 府告第763号 |
| 1346ヘクタール | 80.8% | 320ヘクタール | 19.2% | 令和4年3月28日 | 府告第471号 |
用途地域
用途地域は、将来のあるべき土地利用の姿を実現する手段として、それぞれの地域に見合って、建築物の用途、容積、形態を制限し、地域の性格を明確にするとともに、居住環境の保護、商業、工業その他の都市機能の維持増進を図り、都市の健全な発展を目的として定められています。
| 種類 | 面積 | 百分率 | 容積率 | 建ぺい率 | 外壁後退 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 18ヘクタール | 1.3% | 100% | 50% | 1メートル |
| 13ヘクタール | 1.0% | 150% | 60% | ||
| 小計31ヘクタール | 小計 2.3% | ||||
| 第一種中高層住居専用地域 | 125ヘクタール | 9.3% | 200% | 60% | |
| 第二種中高層住居専用地域 | 318ヘクタール | 23.6% | 200% | 60% | |
| 第一種住居地域 | 352ヘクタール | 26.2% | 200% | 60% | |
| 第二種住居地域 | 129ヘクタール | 9.6% | 200% | 60% | |
| 1.8ヘクタール | 0.1% | 300% | 80% | ||
| 小計131ヘクタール | 小計9.8% | ||||
| 準住居地域 | 4.7ヘクタール | 0.3% | 200% | 60% | |
| 15ヘクタール | 1.1% | 300% | 80% | ||
| 小計20ヘクタール | 小計1.4% | ||||
| 近隣商業地域 | 1.8ヘクタール | 0.1% | 200% | 80% | |
| 45ヘクタール | 3.4% | 300% | 80% | ||
| 6ヘクタール | 0.4% | 400% | 80% | ||
| 小計53ヘクタール | 小計3.9% | ||||
| 商業地域 | 11ヘクタール | 0.8% | 400% | 80% | |
| 準工業地域 | 300ヘクタール | 22.3% | 200% | 60% | |
| 3.7ヘクタール | 0.3% | 300% | 80% | ||
| 小計304ヘクタール | 小計22.6% | ||||
| 合計 | 1345ヘクタール | 100.0% |
|
容積率とは延べ面積を敷地面積で除して得た数値をパーセントで表したもの
建ぺい率とは建築面積を敷地面積で除して得た数値をパーセントで表したもの
特別用途地区
特別用途地区は、用途地域内において特別の目的から土地利用の増進・環境の保護等を計るため定める地域であり、地区内の建築物等の制限については、建築基準法の規定により、地方公共団体の条例により定めることができることとなっています。
本市においては、大阪中央環状線沿いに特別業務地区を決定し、昭和48年11月20日に条例を公布、昭和48年11月25日から施行しています。
| 種類 | 面積 | 告示年月日 | 告示番号 |
|---|---|---|---|
| 特別業務地区 | 22.4ヘクタール | 昭和48年10月1日 | 市告第61号 |
| 特別業務地区 | 24.0ヘクタール | 平成8年1月31日 | 市告第21号 |
| 特別業務地区 | 29.3ヘクタール | 平成18年3月17日 | 市告第52号 |
| 特別業務地区 | 30.3ヘクタール | 平成23年3月29日 | 市告第71号 |
| 特別業務地区 | 25.4ヘクタール | 平成31年3月29日 | 市告第108号 |
高度地区
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
本市においては、住居系地域内の適正な人口密度及び良好な居住環境を保全するため昭和48年10月1日建築物の高さの最高限度地区を指定し、その後、用途地域の変更等にあわせて高度地区も変更しています。
| 種類 | 面積 | 指定地区(最高限度地区) |
|---|---|---|
| 第一種高度地区 | 約 31ヘクタール | 第一種低層住居専用地域 |
| 第二種高度地区 | 約440ヘクタール | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 (一部地区を除く) |
| 第三種高度地区 | 約506ヘクタール | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 第二種中高層住居専用地域(一部地区) |
高度利用地区
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度及び最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
本市においては、昭和55年8月15日河内松原駅南地区第一種市街地再開発事業の計画に伴い高度利用地区を定めました。
| 種類 | 面積 |
建築物の |
建築物の |
建築物の 建ぺい率の 最高限度 |
建築物の 建築面積の 最低限度 |
|---|---|---|---|---|---|
|
高度利用地区(河内松原駅前南地区) |
約 1.6ヘクタール |
45/10 | 20/10 | 7/10(注釈) | 200平方メートル以上 |
(注釈)ただし、表中「建築物の建ぺい率の最高限度」について、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第5項第1号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。
防火地域・準防火地域
防火地域・準防火地域は昭和48年10月1日、市街地における火災の危険を排除するため、商業地域に防火地域、近隣商業地域に準防火地域を指定し、その後、用途地域の変更等にあわせて防火地域、準防火地域も変更しています。
| 種類 | 面積 | 指定する地域 |
|---|---|---|
| 防火地域 | 約11ヘクタール | 商業地域 |
| 準防火地域 | 約1314ヘクタール | 建ぺい率60%以上の地域(一部の地域除く) |
平成25年2月1日から準防火地域の指定を拡大しました
近い将来に予想される大規模地震において、家屋の倒壊とともに大きな被害をもたらすものが広範囲にわたる大規模火災です。
市内には古い木造住宅が多く見られ、火災発生時には延焼の危険性が高く、その被害は大きくなると予想されます。
市街地における火災の被害を最小限に抑えるための制度として、都市計画には「防火・準防火地域」の指定があります。
指定地域では、火災発生時、地域全体に火災が広がりにくいよう、新築や増改築をするとき、建築物の構造に一定の基準を設けています。(別表)
松原市では、用途地域が商業地域(約11ヘクタール)の区域について防火地域、近隣商業地域(約33ヘクタール)の区域について準防火地域を指定していましたが、平成25年2月1日より建ぺい率60%以上の市街化区域(約1,217ヘクタール)について、準防火地域の指定を拡大しました。
つきましては、平成25年2月1日以降に着工する建物については準防火地域の規制がかかります。
また、建築確認申請が平成25年1月31日以前に処理されていても、それまでに着工していない建物は、準防火地域の規制がかかりますのでご注意ください。
準防火地域の構造制限(別表) (PDFファイル: 56.5KB)
防火地域及び準防火地域の指定状況と準防火地域を拡大する地域 (PDFファイル: 2.3MB)
生産緑地地区
生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る制度です。
生産緑地法が改正されました
都市緑地法の一部を改正する法律において、生産緑地法の一部が改正され、生産緑地における行為制限の緩和や、新たに特定生産緑地制度が創設されました。
生産緑地における行為制限の緩和(平成29年6月15日施行)
生産緑地地区内では、住宅や事務所など建築物の新築等や、その他宅地の造成等はできません。
これまで生産緑地地区内で設置可能な施設は、農業用資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができましたが、営農継続の観点から、農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レストランが設置可能な施設として追加されました。
特定生産緑地制度の創設(平成30年4月1日施行)
生産緑地の指定の告示の日(最初の告示は平成4年)から起算して30年を経過した場合、生産緑地はいつでも買取申出が可能となることから、現在適用されている固定資産税等の税制特例措置が適用されなくなります。そのため、引き続き都市農地の保全を図るために特定生産緑地制度が創設され、生産緑地の所有者の意向を基に、市は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できるようになりました。
特定生産緑地に指定された場合、買取申出ができる時期は、「生産緑地の指定の告示の日から30年経過後」から10年延期され、税制特例措置が適用されます。 なお、生産緑地の指定の告示の日から30年経過後は特定生産緑地の指定はできません。
特定生産緑地制度に関する説明会を開催しました
生産緑地の買取申出と行為制限解除
生産緑地の指定の告示の日(最初の告示は平成4年)から起算して30年を経過した場合や、生産緑地に係る主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなった場合は、市長に対して時価で買い取るよう申し出ることができます。(買取申出)
買取申出後、市は庁内関係部署と府に対して公共用地として買い取るかどうかを照会し、買取申出から1ヶ月以内に申出者に対して回答します。
市・府が公共用地として買い取らない場合は農業従事者に対し、引き続き生産緑地としての買取の斡旋を行います。
斡旋の結果、買取希望者が現れず、買取申出から3ヶ月が経過した場合は当該生産緑地における建築や造成といった行為制限は解除されます。
買取申出は、原則として所有する、あるいは主たる従事者となっている生産緑地すべてが対照となりますが、主たる従事者の変更を届け出たものについては引き続き生産緑地として農業従事することができます。(この場合、今後における買取申出理由の対象者は変更後の主たる従事者となります。つまり、今後買取申出ができるのは変更後の主たる従事者が死亡・故障した場合に限られます。)
所有者・主たる従事者の変更
主たる従事者の死亡や故障により、所有者や主たる従事者を変更して引き続き農業に従事することとなった場合は、すみやかに新たな所有者・主たる従事者を届け出てください。