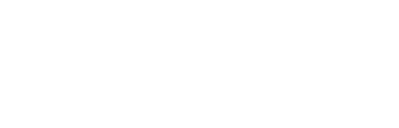AEDを用いた心肺蘇生法(ガイドライン2020)
AEDを用いた心肺蘇生法
安全の確認
誰かが突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合は、近寄る前に周囲の安全を確認します。
反応(意識)を確認する
周囲の安全が確認できたら、傷病者に近寄り反応(意識)を確認します。

耳もとで「大丈夫ですか」または「もしもし」と呼びかけながら肩をたたき、目を開けたり反応があるかないかを確認します。
反応があれば
傷病者の訴えを聞き、必要な応急手当を行います。
反応がなければ
反応がない、あるいはその判断に自信が持てないときはすぐに助けを求めます。
119番通報と協力者への依頼

傷病者に反応がなければ大きな声で、協力者に「あなたは119番へ通報して下さい」
別の協力者には「あなたはAEDを持ってきて下さい」と具体的に依頼します。
心肺蘇生の訓練を受けていない場合でも、119番通報の電話を通して指示をうけ、落ち着いて対応します。電話のスピーカー機能を活用すれば両手が使えるので、指導を受けながら胸骨圧迫などを行えます。
呼吸の確認
傷病者が「普段どおりの呼吸」をしているかどうかを確認します。

傷病者のそばに座り、10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て、「普段どおりの呼吸」をしているかを判断します。
呼吸があれば
反応はないが「普段どおりの呼吸」をしている場合は、吐物による窒息を防ぐため、傷病者を回復体位にします。

回復体位とは
下あごを前に出し、上側の手の甲に傷病者の顔をのせます。
さらに、上側の膝を約90度曲げて傷病者が後ろに倒れないようにします。
呼吸なし
傷病者に「普段どおりの呼吸がない」あるいはその判断に自信がもてない場合は、すぐに胸骨圧迫を行います。
胸骨圧迫

胸骨の真ん中(胸骨の下半)を重ねた両手で、「強く、早く、絶え間なく」圧迫します。

肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、傷病者の胸が約5センチメートル沈むまで。
1分間に少なくとも100回から120回のテンポで絶え間なく30回圧迫します。
圧迫と圧迫の間は、十分に力を抜き、胸が元の高さまで戻るようにします。
人工呼吸
30回の胸骨圧迫が終わったら直ちに気道を確保(空気が口や鼻から肺に達するまでの通路を開く)し人工呼吸を行います。

片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の2本をあご先にあてて、頭を後ろにのけぞらせ、あご先を上げます。
人工呼吸を行います。

気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で鼻をつまむ。
口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして、1回1秒かけて傷病者の胸の上がりが見える程度の量を2回吹き込みます。
うまく胸が上がらない場合でも、吹き込みは2回までとしすぐに胸骨圧迫に進みます。
このとき、胸骨圧迫の中断時間が10秒以上にならないようにします。
心肺蘇生の継続
人工呼吸終了後、すぐに胸骨圧迫を行う。


胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行います。
(30:2のサイクル)
(注意)人工呼吸ができない場合は胸骨圧迫のみを行います。
(注意)救助者が2人以上いる場合は、1~2分を目安に交代します。
心肺蘇生の中断
救急隊に引継ぐまで、または傷病者が目を開けたり、「普段どおりの呼吸」が出現したとき。
傷病者が目を開けたり、「普段どおりの呼吸」がある場合は、回復体位にして経過を観察する。
AEDが到着したら
AED(自動体外式除細動器)の使用方法
心肺蘇生法を行っている途中で、AEDが届いたらすぐにAEDを使う準備を始めます。
AEDにはいくつかの種類がありますが、どの機種も同じ手順で行えるようになっています。AEDは電源が入ると音声メッセージとランプで、あなたが実施すべきことを指示してくれますので、落ち着いてそれに従ってください。
AEDを傷病者の頭の横に置きます。
AEDのふたを開け電源ボタンを押します。
ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。
その後は音声メッセージに従ってください。

傷病者の衣服を取り除き、胸部を裸にします。
胸部に何もない事(アクセサリー、ペースメーカー、濡れている等)を確認し、電極パッドを傷病者の胸部にしっかりと貼り付けます。貼り付ける位置は、電極パッドに絵で表示されますので、それに従って下さい。

電極パッドを貼り付けた後、パッドのコネクターをAED本体の差込口(点滅している)に入れます。
電極パッドを貼り付けると「体に触れないで下さい」などの音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。
このとき、感電の恐れがあるため、「皆さん、離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。

AEDが電気ショックを加える必要があると判断すると、「ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、自動的に充電が始まります。
充電には数秒かかります。
充電が完了すると、「ショックボタン(オレンジボタン)を押してください」などの音声メッセージが流れ、電気ショックを実施することができます。

電気ショック後は、AEDから「すぐに胸骨圧迫を開始して下さい」等の音声メッセージが流れます。
心肺蘇生法再開
心肺蘇生法後は、AEDの音声メッセージに従って下さい。
AEDの使用上の注意点
- AEDは全年齢に使用できます。
- 成人用と小児用の2種類の電極パッドが入っている場合や、成人用モードと小児用モードの切り替えがある場合は、小学生以上には成人用の電極パッド(成人用モード)を使用し、未就学児には小児用の電極パッド(小児用モード)を使用して下さい。
- 成人には、小児用電極パッド(小児用モード)を使用しないで下さい。
- AEDが心電図を解析している時、電気ショックを行う時は、絶対に傷病者に触れないで下さい。
電気ショック時に傷病者に触れると、感電の恐れがあります。 - 電気ショックが必要と解析した場合に、ショックボタンを押さなくても自動的に電気ショックが行われる機種(オートショックAED)もあります。
現在設置されているAEDには、上記の取り扱いと違う場合がありますが、大切なことはその機種のメッセージに従って、電気ショックを行うことです。
これらが応急手当(AEDを用いた心肺蘇生法)の、おおまかな一連の流れです。
このページの説明だけでは、まだまだ不十分です。
消防署では、毎月19日に普通救命講習会を開催しています。
正しい応急手当の知識と技術を身につけるため、ぜひご参加ください。