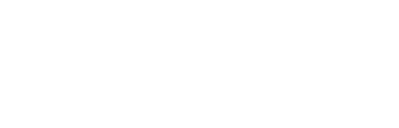- 種類:松原市指定 有形文化財 美術工芸品 彫刻
- 記号番号:彫第1号
- 名称:大林寺 木造 十一面観音立像(だいりんじ もくぞう じゅういちめんかんのんりゅうぞう)
- 員数:1躯(く)
- 時代:平安時代後期(10世紀末から11世紀初め)
- 所在地:大阪府松原市北新町1丁目
- 所有者:宗教法人 大林寺
- 指定年月日:平成21年(2009)2月3日

説明
概要
融通念佛宗(ゆうずうねんぶつしゅう)の布忍山大林寺(ふにんざんだいりんじ)にある本像は、明治6年(1873)に廃寺となった永興寺(布忍寺)の本尊だったものです。頭体幹部をヒノキの一材から彫り出した一木造で、像高は171.5センチメートルとほぼ等身大の仏像です。
深い面奥に比して丸い面貌に浅く目鼻立ちを刻む点や長身で量感をあまり強調しない体躯(たいく)、古様の渦巻状の衣文(えもん)を見せる特徴は、10世紀彫刻のなかでも「奈良系仏像」と称される一群と共通したものです。
本像の作製は平安時代後期(10世紀末から11世紀初め)と推察されますが、そうすると寛治3年(1089年)の創建と伝えられる永興寺(布忍寺)の時期よりも古いことになります。おそらく永興寺(布忍寺)創建以前に前身となる堂宇に安置されていたものか、もしくは寛治3年(1089)の創建に際して別の地より移坐されたと考えられます。
本像は市内ではもっとも古い仏像のひとつで、府下においても中央様式を示した等身をこえる十一面観音立像は一部の古刹(こさつ)を除いては稀で、南河内地方における仏教文化を考える上で貴重な文化財です。
資料
松原市文化財指定調書_彫第1号 を見る/PDFファイルを開く (PDFファイル: 1.7MB)
たじひのだよりNo.9 を見る/PDFファイルを開く (PDFファイル: 3.8MB)