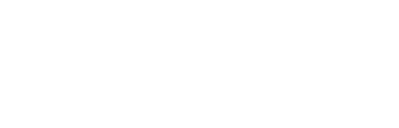高額療養費って?
病院などの医療機関で支払った保険診療の一部負担金が高額になって、基準額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分があとから国民健康保険より支給される制度を、高額療養費制度といいます。
いつ返ってくるの?(後期高齢者医療制度対象者は除く)
高額療養費の払い戻しの対象となる場合は、診療を受けた月から最短で3ヶ月後に申請書を送付しますので、それまでに申請はいりません。払い戻しの方法は、口座振り込み(世帯主名義に限る。)となりますので、申請書に必要事項を記入し、押印して、同封の返信用封筒にて返送してください。申請書がこちらに届いてから1ヶ月から1ヶ月半後に振り込みさせていただきます。
高額療養費の申請手続きが簡素化されるようになりました
高額療養費の払い戻しの対象となった場合、市役所より送付される高額療養費の申請書で、初回のみ高額療養費の申請手続きをすれば、2回目以降は申請手続きが不要となります。2回目以降は、初回に指定された世帯主口座に自動的に振り込みを行います。
ただし、以下に該当される場合は簡素化されず、毎回支給申請手続きが必要となります。
●保険料に滞納があるとき
●世帯主が変更となったとき
●登録されていた世帯主口座を解約したとき
●国民健康保険の被保険者番号が変更となったとき
※ご自身で簡素化の解除を希望される場合は、保険年金課までご連絡ください。
返ってくる金額は?
同じ月に同じ医療機関で自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったときは、超えた分について支給されます。
一つの世帯で同じ月に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払い、その額が合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた分について支給されます。
一つの世帯で、過去12カ月以内に4回以上高額療養費に該当するときは、4回目以降は自己負担限度額が、1カ月それぞれ140,100円(基準総所得901万円超世帯)、93,000円(基準総所得600万円超から901万円以下の世帯)、44,400円(基準総所得600万円以下の世帯)、24,600円(住民税非課税の世帯)となり、それを超えた分について支給します。
限度額適用認定証について
入院だけではなく外来診療でも限度額適用認定証が使用できます。対象となる医療機関は保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受診された保険診療が対象となります。(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です)限度額適用認定証を提示すると医療機関での1ヵ月毎のお支払いが下記の限度額で止まります。
自己負担限度額(月額)について
| 対象世帯 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 基準総所得額901万円超 | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
| 600万円超から901万円以下 | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
| 210万円超から600万円以下 | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
| 210万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
| 対象世帯 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 基準総所得額901万円超 | 140,100円 |
| 600万円超から901万円以下 | 93,000円 |
| 210万円超から600万円以下 | 44,400円 |
| 210万円以下 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 対象世帯 | 自己負担限度額 | 限度額適用認定証の申請 | |
| 外来 | 外来 + 入院 | ||
| (個人ごと) | (世帯単位) | ||
| 現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) (4回目以降は140,100円) |
必要なし | |
| 現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) (4回目以降は93,000円) |
必要 | |
| 現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) (4回目以降は44,400円) |
||
| 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
必要なし |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 必要 |
| 低所得者1 | 15,000円 | ||
※ 区分が「現役並み3」・「一般」の人は、高齢受給者証にて代用可能ですので、申請の必要はありません。
【70歳以上75歳未満の人の所得区分について】
●現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人のことです。
| 条件1 | 70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満。 |
| 条件2 | 70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満。 |
| 条件3 |
70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。 |
| 条件4 | 70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額等-基礎控除33万円)の合計額が210万円以下。 |
●一般 ・・・ 現役並み所得者、低所得者2・1以外の人。
●低所得者2 ・・・ 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
●低所得者1 ・・・ 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
一部負担金減免制度について
保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる特別な理由がある場合に、医療費の一部負担金の減額・免除・徴収猶予を受けることができる場合があります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。