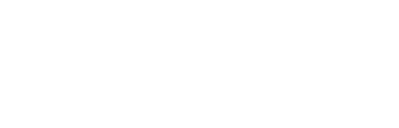- 名称:立部遺跡火葬墓出土須恵器蔵骨器(壺・蓋)附火葬骨ほか火葬墓内遺物 (たつべいせきかそうぼしゅつどすえきぞうこつき(つぼ・ふた) つけたりかそうこつほかかそうぼないいぶつ)
- 種類:松原市指定有形文化財 美術工芸品 考古資料 考第1号
- 員数:一括
- 時代:平安時代初期(9世紀前半)
- 所在地:大阪府松原市阿保1丁目1番1号
- 所有者:松原市
- 指定年月日:令和4年(2022)9月29日


須恵器蔵骨器蓋。写真上は真上から撮影したもの。高さ3.0センチメートル、直径12.5センチメートル。

須恵器蔵骨器壺。頸部に蓋と壺を固定していた粘土が付着している。高さ23.6センチメートル。

須恵器蔵骨器壺のX線CT画像。赤色が壺で紫色が火葬骨。

火葬墓の蔵骨器埋納状況。土層観察用の畦に見える黒い部分が土・焼土混じりの炭。

火葬墓の墓壙(ぼこう)に充てんされた土・焼土混じりの炭を全て取り除いた状況。写真中央の蔵骨器の右側にあるのが土師器杯。
説明
概要
本資料が出土した立部遺跡は、松原市立部などに位置する縄文時代~近世の集落跡・社寺跡・古墳・その他の墓・生産遺跡です。本資料は平成2年(1990)に立部3丁目399-1ほかに所在する松原市立大塚青少年運動広場の施設整備工事に伴って実施した発掘調査で出土しました。
この調査では、古墳時代中期~後期の古墳7基、飛鳥時代の土壙墓(どこうぼ)1基、奈良時代の火葬墓1基、平安時代初頭の火葬墓1基、平安時代前期の土壙墓1基・木棺墓(もっかんぼ)1基が見つかり、古墳時代中期~平安時代前期にかけての在地氏族の墓地であることがわかりました。その後、平安時代後期~鎌倉時代には、掘立柱建物や井戸が営まれていることから、このときまでに墓地とは認識されなくなったようです。
蔵骨器は一辺約1m四方の平安時代初頭の火葬墓から見つかりました。全体ではありませんが、周囲は土混じりの木炭で埋められており、壺と蓋は粘土で固定されていました。同じ火葬墓内からは9世紀前半の特徴をもつ土師器杯(はじきつき)が出土しました。
壺は短頸壺(たんけいこ)で、口縁部(こうえんぶ)・頸部(けいぶ)の形が畿内(きない)地域のものと異なっています。蓋も輪状(りんじょう)つまみをもつ点が、畿内地域のものとは異なっています。したがって、壺・蓋とも畿外(きがい)で生産されたものと考えられます。
壺内部の埋納物を確認するため、X線CT撮影と取り上げ作業を実施したところ、壺の上部まで火葬骨と若干の木炭・焼土が納められていましたが、副葬品はありませんでした。
火葬骨を専門家に鑑定いただいた結果、40~59歳の男性1体分とわかりました。骨量は全身の約半分で、上腕骨などの四肢骨(ししこつ)がほぼ丸ごと、頭蓋骨も約半分が埋納されるなど、例外的に多くの量が納められ、残存状況も良好でした。骨に亀裂や捻じれが認められることから、筋肉が残存した状態で火葬されたことがわかりました。また、推定身長は158~160cmで、骨の発達状況から上半身をよく使用する生活様式が推定されました。
さらに、分析機関に依頼し、火葬骨を対象に放射性炭素年代測定(ほうしゃせいたんそねんだいそくてい)・ストロンチウム同位体分析(どういたいぶんせき)などを実施した結果、被葬者(ひそうしゃ)は800年ごろに死亡し、比較的栄養度の高い食事を摂っていたことがわかりました。このほか、火葬後に混入したとみられる壺内部の焼土や遺跡の土なども分析し、これらが同じ地質のものと考えられるため、火葬自体は立部遺跡周辺で行われたと推定されました。
本資料は、古墳時代中期~平安時代前期にかけて連綿と営まれた在地の氏族墓地内の火葬墓から出土したもので、この火葬墓は、封土(ふうど)など上部構造は残存しないものの、下部構造は埋葬施設、蔵骨器ともに良好な状態で残されていました。また、蔵骨器の壺と蓋が粘土で密封されていたことにより、男性1人分の約半分という例外的に多量の火葬骨が当時の状況を保って納められていました。このように良好な状態で発掘され、被葬者や埋葬方法について多くの情報を得ることができた例は少なく貴重です。
本資料に納骨された男性の身分については、火葬墓の構造、蔵骨器のほか他遺跡の事例から、従五位以下の官人を輩出するような下級氏族の出身者と考えられます。
調査地は古代の河内国丹比郡(かわちのくにたじひぐん)にあたり、被葬者の出身氏族としては古くから葬送(そうそう)に関わる職掌(しょくしょう)を担った土師氏(はじし)や画師(えし)を務める官人を輩出した河内画師(かわちのえし)などが考えられます。両者の本拠地と考えられる丹比郡土師(はにし)郷(里)は、堺市域と松原市域に比定する説があり、松原市域では松原市立部周辺が比定されています。本火葬墓に直接関わる文献史料は確認されておらず氏族名は不明ですが、少なくとも古くから立部周辺を本拠とした氏族の墓であったと考えられます。
本資料は古代の丹比郡における葬送儀礼(そうそうぎれい)や在地氏族の墓制(ぼせい)の一例を示す貴重な考古資料であり、今後、研究する上で基準となる資料であることから、本市指定文化財に相応しいと考えられます。
資料
松原市指定文化財調書 立部遺跡火葬墓出土須恵器蔵骨器(壺・蓋) (PDFファイル: 4.3MB)
関連するページ
外部リンク
書籍・雑誌など
松原市文化財報告9:立部遺跡・立部古墳群(独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所/全国遺跡報告総覧)

このページで公開している画像と文章は CC BY 4.0(クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス)の下に提供されています。 出典を明記することで、自由に利用することができます。二次利用の制限はありません。利用される方はライセンスの内容をご確認ください。